この記事を読むとリアルなOEM技術開発屋の現状の心の内が少し分かります。生活の足をサポートする乗り物であり、お気に入りの相棒となっていく乗り物にどんな安全サポートを仕様として付与しておけばいいか。短くても5年6万キロ、長ければ20年は現役として走り続けるクルマの安全装置とAD/ADASについて考えます。
1. 高齢者の移動手段問題

最近、地方の高齢者が運転するクルマの交通事故が注目されています。狭い道でのハンドル操作不良、アクセルとブレーキの踏み間違え、そして高速道路の逆走、急な体調不良による無意識運転など。でも実際にはクルマが無ければ病院や毎日の買い物など移動が困難になりその対応は高齢化社会が進む中でますます難しい課題となっています。私の親は74歳で運転免許返納しました。その後は電車やバス、歩きですべての移動を行っていましたが、自由な移動が出来なくなりだんだんと外出の機会は減ってしまっていました。外出しなくなると、体を動かす事自体が減ります。高齢者にはまさに負のスパイラルです。高齢者こそ自由な移動の喜びを与えてくれるパーソナルモビリテイが必要です。特にこの10年は実現できそうで実現できていないこの高齢者の自由な移動について。どのようにしたらよいのでしょうか。
👉関連記事 世界でいまメジャーに走ってるくるまシリーズ国内OEM必見!2024年3月最新 オーストラリア シドニー メルボルン キャンベラで見たクルマ!
2. みんなお気に入りのモノで自由に移動したい

私は30年以上、バイクとクルマの特に動力源の研究開発/生産製造に携わってきました。20~30代はバイク、40~50代はクルマ。その中でも40代中盤から50代の現在には内燃機関から電動に関わっています。その中で感じるのは多くの人は基本的には自分で好きなように運転したい、好きなところに移動したいという気持ちです。思い通りに乗り物を動かしたい操りたいという気持ちです。老若男女、年齢は関係ありません。ここに寄り添わなければ、ただ単に自動運転の乗り物では世の中の人々に受け入れてはもらえないのだろうなと考えています。

👉合わせて現役世代は読みたい!高齢者の方が実は知ってる!?超初級編!2ストロークキャブセッテイング エアスクリュー調整
3. それぞれの心地よさの追求、新技術と大量生産の壁

たとえばe-Axleはそのモーターから発生する圧倒的なトルクでエンジン+ミッションでは到底実現しなかったような俊敏な走りを実現します。しかし、実際の開発現場では『なにか味気ない出力特性を補いたい』『多段変速のような特性が欲しい』『なにか走りに見合った音が欲しい』など、人の感性に寄り添うような開発が続いています。EVとしての効率は落としてでも、乗る人、運転する人が『心地よいなにか』を求めて開発が続いています。自分の手足のように動く乗り物になれば、それが手動操作であっても自動運転であっても、そこには明確な線引きは無さそうです。
上記のようなEVにも操る喜びを最新技術で達成する開発を続けるなか、相反する問題もあります。バイクやクルマの開発には多大な時間と費用がかかりそれを販売し回収するためのライフサイクルが現実的に存在します。1台数百億円の開発費。それを数年数十万台生産し回収し利益を出す。同時にその車は5年から15年の耐久性を持ち合わせているため、通常は1台の車を開発すると、10年から20年はその時代のその技術の仕様で世の中のユーザーは現実的に乗ることになるのです。どんなに先進技術を盛り込んでも、おそらくその商品寿命の半分以上は時代遅れな機能のままで生涯を全うするのが普通です。

上記のような現実的なユーザーを想定すると、相当なアップデートが可能なくるまでなければ、今この時代のパーソナルモビリティに求められている技術の進化を伴う運転サポート機能には到底到達できませんよね。

もはや ”クルマの後から進化”というレベルではなく、AIロボットを助手席に同乗させ教習所の路上訓練を行うようにサポートしてもらうことを考える方が合理的です。

👉関連記事 2R/4R関係なく内燃機関共通のトラブルシューテイング!バイクのエンジンがかからないときのチェックポイント|原因別対処法まとめ
4. 末永く、人、モノを大切にするための新技術でありたい
私が提案するのは、次の3つの方向性です。
① あくまでも自分で好きな時にすぐ運転できるものモノ
② 新車のクルマに初期搭載する安全運転先進技術ではなく、同乗してくれるAIロボットのような安全サポート。
③ 運転適性能力(免許)は同乗(搭載)するAIロボットの安全サポートの能力とセットで適正判定。
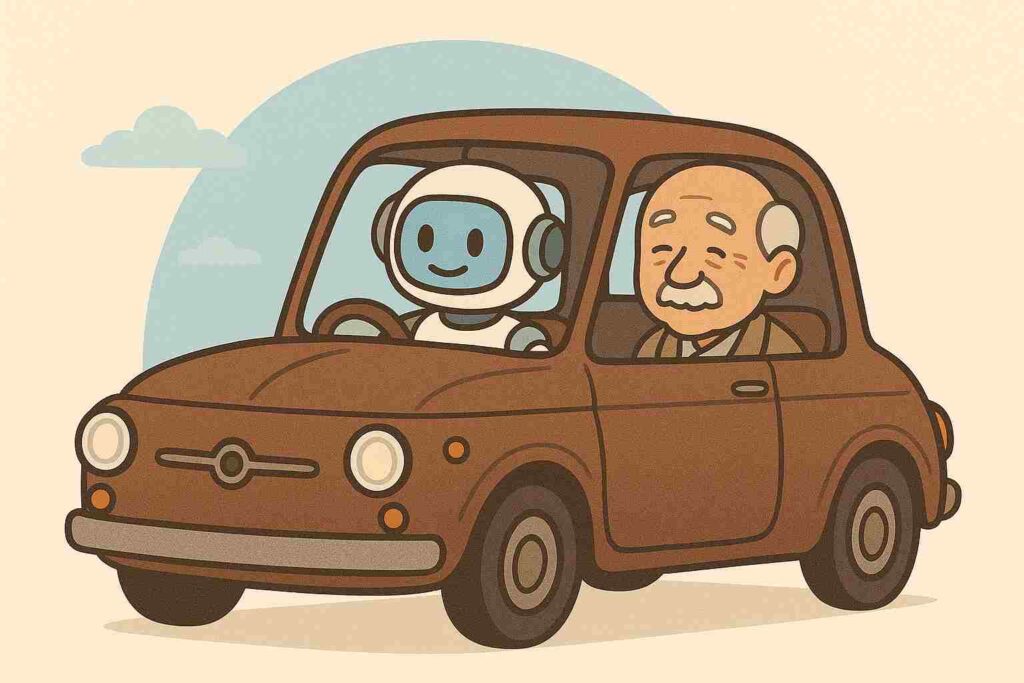
5. まとめ
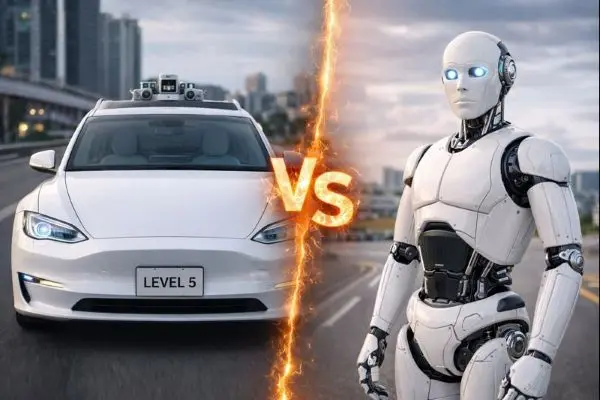
これからの技術者に必要なのは、“合理性”と“社会の見方”の両立かもしれません。
昨今、乗り物の世界は大きく進化しています。これによって各国法規も改定されています。卵が先か鶏が先か議論になりますが、重要なのは世の中の人が何に困っているか、何が欲しいのか?そして何は必要ないのか?よく観察してそれを叶える技術者は新しいアイデアを提案することだと思っています。
世の中の要求に時間軸も含めていかに合理的な提案ができるかどうか。
皆さんはこれからの世の中にはどんな乗りものが必要だと思いますか?ぜひご意見をください。
それではまたね!
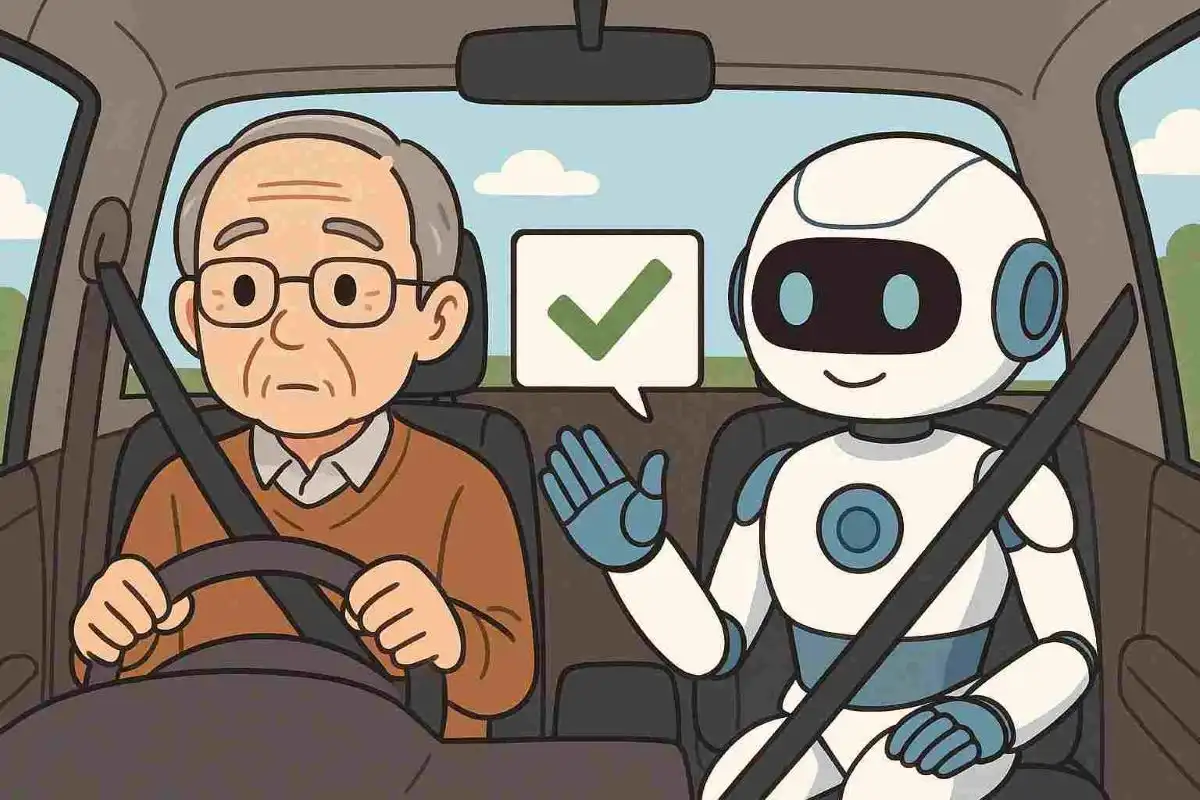




コメント